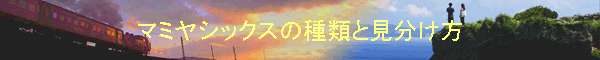マミヤシックスの種類と見分け方
 |
|
マミヤシックス
P型(左)とオートマット型(右) |
予め申し上げると、 私はクラシックなカメラにはズブの素人である。
以下、
そのような者が実用品としてマミヤシックスを購入した際に指標とした各モデルの見分け方。
前提
何しろ素人だから、 コンディションに関してさほどの目利きなどできるはずがない。
ただ、 古いものより新しいものの方が良い状態である 「確率が高い」 のは言うまでもない。
目利きの腕が同じなら年式の若いモデルの方が 「ハズレ」 る可能性が多少は低くなるということだ。
幸いマミヤシックスは結構タマ数が多いので、 年式が若い最終グループに絞って選ぶことにした。
もちろん本当の目利きとはコンディションの悪い若い個体ではなく古くてもコンディションの良い個体を見抜く技量のことだが、
残念ながら私はそのような目を持っていない。
正面から見て四角い窓が二つ並んでいれば最終製品グループなので、 一目で見分けが付く。
マミヤシックスの種類
窓が角窓2つのものが最終製品グループで、 6種類のモデルがあるようだ。
レンズは何種類かあるようだが、 どれも75mm F3.5である。
| タイプ |
名称(型) |
セルフ
コッキング |
自動巻止 |
二重露光
警告 |
スタート
マーク式 |
6×4.5
兼用 |
最高
シャッター
速度
|
レンズ |
発売年 |
| A |
P |
× |
× |
× |
× |
× |
1/300 |
セコール |
1957年 |
| KII |
○ |
1/500 |
1956年 |
| B |
IVB |
× |
○ |
○ |
× |
× |
1/500 |
ズイコー |
1955年 |
| IVS |
セコール |
1957年 |
| C |
オートマット |
○ |
○ |
-
(不要) |
○ |
× |
1/500 |
ズイコー |
1955年 |
| オートマットII |
セコール |
1958年 |
※ 「タイプ」は筆者による勝手な分類。
※ シャッターやレンズは生産の都合で異なる物を使用することもあったとか。
タイプA
機能を絞った廉価版。
最終グループ唯一の6×6判・6×4.5判兼用機「KII」がある。
より古いグループでは自動巻き止めかつ6×4.5兼用というものもあったようだが、 最終グループには存在しない模様。
P型は最終グループでは唯一、 シャッターの最高速度が1/300秒まで。
タイプB
マミヤシックスとして一般的な機能を持ったグループ。
-
自動巻き止め
フィルム巻き上げ時、 1コマ分進めると自動的に止まる。
-
フィルムセット時、 1コマ目までの送りは赤窓による目視
-
二重露光防止(警告)機構
シャッターを切るとファインダー内に赤い幕が現れ、 フィルムを巻き上げると引っ込む。
タイプC
タイプBのような一般的なマミヤシックスに、 主にセルフコッキング機能を搭載したもの。
-
セルフコッキング
フィルムを巻き上げると自動的にシャッターがチャージされる。
-
自動巻き止め
-
フィルムセットがスタートマーク式
フィルムのスタートマークとボディのマークを合わせて巻き上げていくと自動的に1コマ目で止まる。
-
二重露光防止(警告)機構なし
そもそもセルフコッキングなのでフィルムを巻き上げなければシャッターがチャージされず、
普通に使えば二重に露光してしまう心配はない。
(ただし手動でシャッターをチャージすることはできる)
マミヤシックス 最終グループの見分け方
詳しい人がどう見分けているかはわからないが、 以下、
機能という側面から見分け方をまとめてみた。
このような、 必然的に機能の違いから生じる外見の違いだけでは完全に特定するのは無理だが、
逆に手に入れたけれど必要な機能が付いていなかったということにはならないはず。
なお、 私がフラフラとカメラ屋を覗いてみた印象では、 最終グループの製品に限ると、 機能的に中間に位置するタイプB (自動巻き止め・非セルフコッキング
のIVB・IVS型) を目にする機会が一番少なかった。
廉価な赤窓式のタイプA (P型、KII型) とフル装備かつ最終型ではないオートマット型は結構見掛ける。
P型購入後、 自動巻止めや二重露光防止のための機構が欲しくなって更に探してみたのだが、 結果、 最初に見付かったのは機能フル装備のオートマット型だった。
・・・
数ある6×6判スプリングカメラでマミヤシックスを選んだのは、
このカメラの最大の特徴である「バックフォーカシング」 というピント合わせ機構によるところが大きい。
今後きっと他のカメラも買ってしまうんだろうけど^^;
通常、 スプリングで繰り出したレンズを更に前後に動かしてフォーカシングするところ、
マミヤシックスではフィルムの像面を前後させるようになっている。
つまり、 カメラの開閉操作以外ではレンズは一切動かない。
距離計とフィルム像面の連動ならボディの中だけで完結するので、 いかにも壊れにくそう。
しかもピント合わせのためのリング類もボディ側にあれば済み、 右手親指で操作できる位置にピントノブが付いている。
レンズ周りを触る機会が減るので蛇腹も長持ちしそうで、 実用用途ならメリットは多いと思う。
唯一の欠点はコマ間が不揃いになることか。
なお、 説明書によると、
『現像済みフィルムの画面の間隔は、 多少ふぞろいですが、
これはフィルムを動かしてピントを合わせるというマミヤシックスの特徴の結果でして、
なんらさしさわりがないように設計されておりますから、 御安心ください。』
とのこと。
内容はさておき文体に何とも味がある(笑)
(参照サイト:Mamiya6/マミヤシックス
オートマット : 取り扱い説明書 ……てぬぐいぶろ……)
|