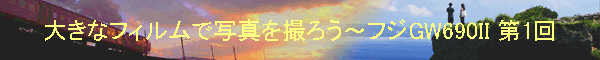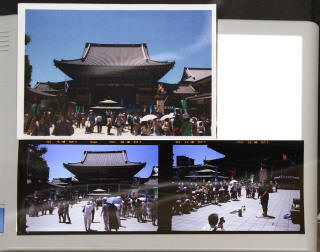大きなフィルムで写真を撮ろう〜フジGW690II 第1回あらかじめ申し上げておくと、 このページは、 ほとんどデジタルしか知らない坊やが書いている (年齢は坊やじゃないが^^;)。 なので、 既に中判やそれ以上のフィルムで写真を撮っている人にとっては当たり前のことしか書かれていないはずである。 さて、 私はほとんどデジタルでしか写真を撮らないのだが、 フィルム写真自体にはずっと関心は持っており、
時折古いフィルムカメラを持ち出したりしていた。 それもあってフィルムで撮る機会が大幅に減っていたのだが、
フィルムでの撮影にこだわっている人というのは、
表現力や画質というよりも撮影スタイル … 現像するまで結果はわからないので必然的に一枚に込める気持ちが強くなる等 …
にこだわっているという面が強いように思う。 …と、 まぁ、 そんな大げさな話でなくても、 単純にいつもと違う機材で撮るというのも楽しいものなのだ。 私の場合、 どうせフィルムで撮るならデジタルでは不可能な大きなフォーマットで… と思っていて、 そういう点では6×4.5判 (像面56×41.5mm) ではちょっと物足りず、 6×7判 (同69×56mm。 長辺で135判の2倍弱) あたりがいいなぁ、 などと考えていた。 6×7の一眼レフはバカでかくて重いので、 買うならレンジファインダーのMamiya7シリーズ (リンク先はMamiya7 II) にしようと思っていたのだが、 どんなシステムでもボディとレンズを揃えるのは(経済的な面で)重荷だし、 メインであるデジタル一眼レフ一式と両方のシステムを持ち歩くのは物理的に厳しいものがある。 そこで目を付けたのがフジのレンズ固定式の中判カメラ。 フォーマットは6×7cm、 6×8cm、 6×9cmと各種揃っているが、 「どうせなら一番でかいフォーマットにしてしまえ!」 と、 ランニングコスト(フィルム・現像代)無視、 勢いだけで6×9判のGW690 II Professionalに決めてしまった。 レンズは90mm F3.5で、 6×9判では準標準レンズとなる。 135判での約39mmに相当。 この画角のせいもあってか、 昔は集合写真御用達カメラだったようだ。 このカメラを選んだ理由はいくつかある。
サイズ比較用に、 EOS5Dに標準レンズ (EF50mm F1.8 II) を装着したものと並べてみた。
なお、 GW690シリーズには初代、 II、 IIIがあるが、
少しずつリファインされただけで基本的な性能・機能は何も変わらない。 また、 GW690の兄弟機として、 65mm F5.6の広角レンズ (135判での28mmの画角に相当) を搭載したGSW690シリーズというのもある。 レンズ以外は基本的にGW690シリーズと同一で、 少なくともGW690 IIとGSW690 II、 GW690 IIIとGSW690IIIはマニュアルも共用である (マニュアルに、 両機の違いはレンズだけなので説明書を兼用しています、 という断り書きがある)。 画角が広い方が広大な風景など大きなフォーマットでより楽しめる写真が撮れそうだが、 デジタルと違って写り込んでしまったものをゴニョゴニョはできないので画角が狭いGW690を選んだ (ヘタレ…)。 流通量もGW690の方が圧倒的に多いようである。 露出計について私の場合このカメラを単独で持ち歩くことはまずないと思われるので、
露出計を内蔵していないことはほとんど問題にならない。 ただし、 デジカメを露出計として使う場合、 実際の感度がフィルムより大幅に高かったり低かったりするものも結構あるようなので、 事前にテストしておく必要はある。 実際には、 それに加えてフィルムによる実効感度の違いや、 長時間露光ではフィルムの相反則の影響もあるが、 これは露出計を使っても同じことだ。 実写してみるちゃんとシャッター速度が出ているか (露出が狂わないか) をテストしたいということもあって、 120のリバーサルフィルム (ベルビア100F) を入れて初撮影をした。 なお、 ちゃんとフィルムの入れ方を守らないと、 1コマ目が半分切れたり、 フィルムのお尻が未露光のまま残ってしまったりする (←やっちまった人^^;) 実は試写の前に中古店でこのカメラの取説を見付けたのだが、 高いので買わなかった。 テスト撮影で数コマ無駄にしてもその方が安上がりだし…。 新宿に 「取説見るだけ50円」 なお店もあるが… で、 撮り終わったら早速現像となるのだが、
ブローニーのリバーサルを即日現像してくれるお店はほとんどないようだ。 今日現在では、
新宿西口のカメラのキタムラでは120フィルムのリバーサルに限り即日現像してくれる。 … 仕上がりまでの間カメラ屋を巡って暇を潰し … その間にも買い物してしまう危険を伴うが^^; … 2時間後に仕上がったフィルムを受け取った。 仕上がりを見てピントが怪しかったらその場でカメラの無限遠をチェックしようと考えていたので、 電池でも使える小型ライトボックス (ってこれしか持ってないのだけど^^;) とルーペを持参していた。 近くの喫茶店でおもむろにライトボックスを取り出し、 ポジを眺めてみる。 うーん、 美しい。 ライトボックスの上で見るポジというのは独特の美しさがあるが、 撮像面82.6mm×56mmともなるとルーペを使わず肉眼でも楽しめる。 6×9判の像面は、 120/220フィルムの幅方向が長辺となる6×4.5判のおおよそ2倍もの大きさだ。 とりあえず…何と、 今回はこれで終わりなのだ。 私もまだ120フィルム1本しか撮っていないので、 わかったようなことは何も言えない。 とりあえず今回は 「でっかいポジって面白そうでしょ?」 ということで^^; 中判ともなると 「知っている人は当然のように知っている」 からなのか、 フィルムの入れ方なんていう初歩中の初歩についてはあまりネット上には情報がない。 でも、 フィルム時代から長く写真をやっている人でも、 135フィルムしか使ったことがないという人は結構いると思う。 なので、 次回以降、 肝心のフィルムの入れ方など少しは役に立ちそうな情報を載せたいと思っている。 文章でわかりやすく説明する自信がなく、 写真を準備したりするのにちょっと時間がかかりそうなので… 追記大きなフィルムで写真を撮ろう〜フジGW690II 第2回 フィルムの入れ方を掲載しました
|
コメント機能は終了しました。
このコンテンツへのコメント(4)
関連記事
|
カメラ,中判,フィルム,フジ,FUJI,GW690II Professional,GW690 II Professional,使い方,リバーサル,ポジ,現像,大きさ