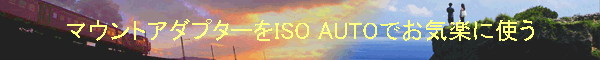マウントアダプターをISO AUTOでお気楽に使う
マウントアダプターのメーカーの公式HPを見ても、
使用できる撮影モードは絞り優先もしくはマニュアルと書いてあることが多いが、
デジタルボディの場合は必ずしも最適ではないと思うことがある。 なお、 以下はNEX-3にM42レンズ用マウントアダプタを装着した場合に基づいて書いている。 マウントアダプターと露出モードマウントアダプターは絞り優先で、 という決まり文句はもちろん間違いではない。 フィルム時代なら。 フィルムカメラではフィルムを装填した時点で感度が決まっており、 ボディからレンズの絞りをコントロールできないという状態ではボディがシャッター速度を変化させる絞り優先モードで露出をコントロールするのが唯一の方法だった。 しかし、 最近はデジタル一眼でもISO感度自動モードが付いているのが普通で、 手持ちで気軽に撮影するならISO AUTOを使わない手はない。 ところが、 マウントアダプター使用時は絞り優先モードでは都合良く手ブレしない感度
に設定してくれるとは限らない。 ISO AUTOでお気楽手持ち撮影それを回避できるのが、 マウントアダプターの使い方の基本には名前が出てこないシャッター速度優先モード。 シャッター速度優先モードを選んで感度オートを選択、
レンズ側で自分の描写意図に合った絞りに設定。 今更言うまでもなく、
本来シャッター速度優先モードは設定されたシャッター速度で適正露出になるようにカメラが絞りを変化させるモードだが、
マウントアダプタ経由ではボディは絞りをコントロールできず、 シャッター速度も撮影者が設定した値になるため、 ボディは感度
だけを変えて露出を制御するというわけだ。 理屈上はマニュアル露出 (Mモード) でも感度の変更による露出制御は可能なはずだが、 少なくともNEX-3ではMモードではISOオートを選択できない。 「マニュアル露出なのにAEが適正露出を決める」 というのは確かに馴染みにくいのかも。 なお、 NEX-3ではオート時の上限がISO1600相当に固定されているが、 感度オートの上限を変更できる機種なら画質にも配慮したより柔軟な使い方が出来てなお美味しいだろうと思う。 例外これで全てうまく行きそうに思えるが、 ちょっと考えるとこれだけでは対応できない状況があることに気付く。
このような場合にはそのままでは適正露出にならない。 (※ マウントアダプタ使用時は 「F--」 の表示になるがこれが点滅する) NEXとマウントアダプター少なくともNEX-3では、
マウントアダプターをISOオートで使おうと思ったらシャッター優先モードしかないと思うのだがどうだろう。 何度か書いているが、 NEXのユーザーインターフェースは誰にもフレンドリーではないと思う。 NEX-6やNEX-7を見ると上位機種については一眼レフ等に近いものにする方向性のようにも見えるが、 入門機もそうあるべきだと思う。 なおNEX-3の場合、 お気楽撮影の最終兵器 「手持ち夜景」
では完全オートになってしまい、
マウントアダプター使用時は最適なシャッター速度に設定されないためか完全には機能していないように思われる。 |
コメント機能は終了しました。
このコンテンツへのコメント(0)
| NEX-M42 | EOS-M42 |
|
|
関連記事 |
マミヤ6,mamiya6,mamiya-6,マミヤシックス,見分け方,カメラ,中判,スプリングカメラ,蛇腹式カメラ,フォールディングカメラ,ブローニー